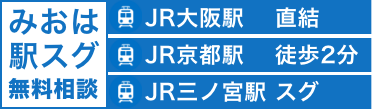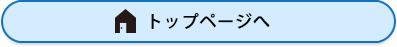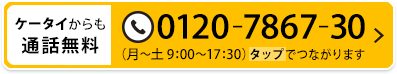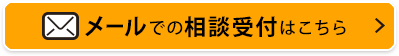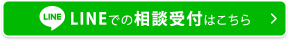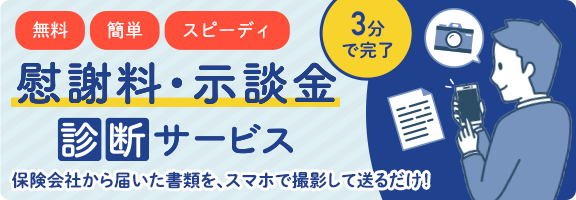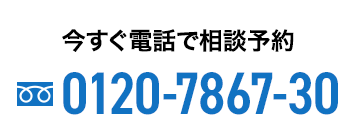遷延性意識障害の賠償請求に役立つ
様々な情報をご紹介しています。
04症状固定を、いつにするのか?
- このページのポイント
- 症状固定の診断は医師にしかできませんが、ある程度なら相談できる場合があります。症状固定のタイミングについての注意点についてご説明します。
症状固定をすると自己負担が増える
①症状固定のタイミングとは?
保険会社は早めたがりますが、要注意です。
症状固定をすると、治療費や休業補償が打ち切られます。そのため、保険会社は早い時期に症状固定を促してくることがありますが、症状固定の診断は医師にしかできません。医師の判断をもとに適切な時期に症状固定にする必要があります。


➁自己負担の問題
症状固定後は、治療費が自己負担となり、介護に入る場合も金銭的な負担が増えます。

症状固定になると、後遺障害等級の認定を受けて賠償金などを受け取るための次のステップに進みますが、退院を促されることもあり、介護に切り替えることになります。
介護にする場合、自宅介護なのか施設介護なのか、自宅介護であれば誰が介護するのか、その人員の確保や住まいのリフォーム(介護ベッドを置くスペースの準備)などのプランが必要となります。賠償金を受け取る前に、大きな金銭的負担が発生するわけです。解決するまで、そのやりくりが可能かどうかの見通しを立てなければならず、難しい判断をしなければなりません。

慰謝料・賠償金を受け取るまでのやりくりをどうするか

遷延性意識障害の場合、賠償金が大きくなる分、実際の受け取りまでには時間がかかります。そのため、それまでにかかってくる費用負担に対応する必要があります。
まず、自賠責保険への請求を検討しましょう。後遺障害等級が認定されれば、最大4000万円の支払いを受けられますので、ある程度の長期にわたり経済面での不安は解消されます。ただ、自賠責の支払いにも症状固定からしばらくの時間が必要です。自賠責受け取りまでについては、治療費を抑えるための制度を活用したり、各種補助金(特別障害者手当の受給等)を活用する必要があります。

増額しなければ
弁護士費用はいただきません!
※弁護士特約の利用がない場合